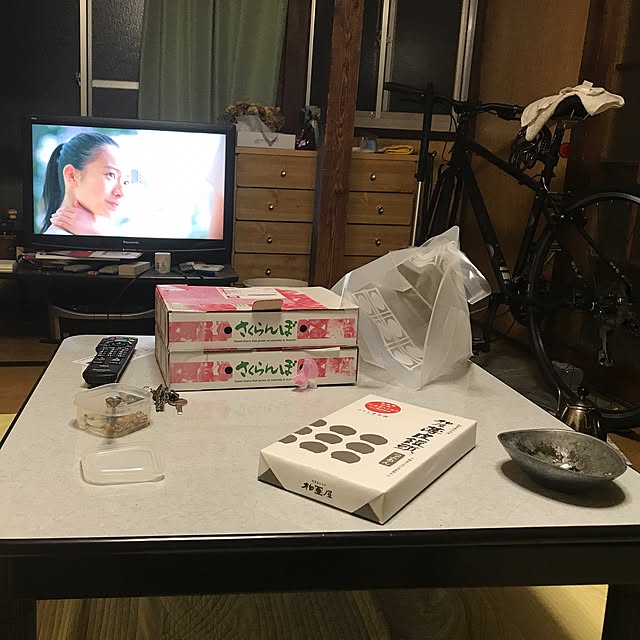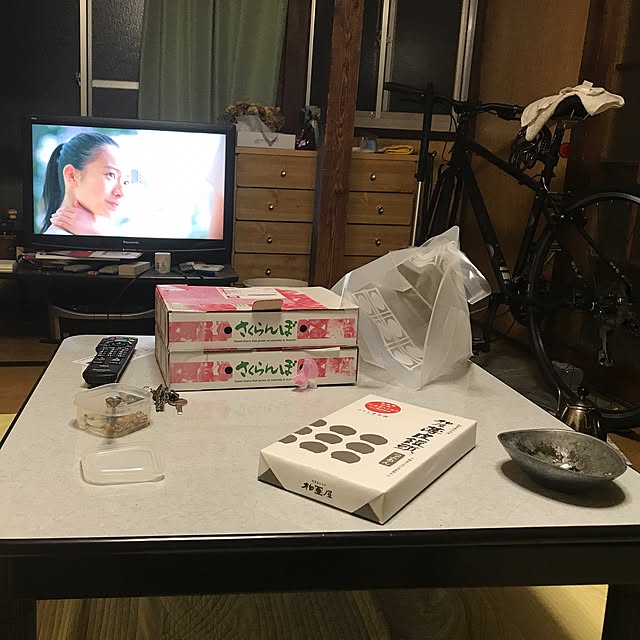おはようございます♡
暮らしのひとこま♡
朝の風景✧
幼稚園に送り出す前の我が家のキッチン✧
冬でも麦茶しか飲まないので、水筒に麦茶いれて、おはしセットをカウンターの上に✧
置いとくと自分達で水筒カバーにいれたり、お給食袋におはしセットいれたりしてくれてます(*ᵕᴗᵕ)
朝一気に麦茶がなくなるので、朝食後に朝は麦茶づくりしつつ洗い物すませてます(´,,>ω<,,`)
べびちゃんはここだとキッチンにいるときはもちろん、白いドアの向こうはすぐ洗面所なので、ドアあければあたしが歯磨きや顔あらうのも見えるし、洗濯物もおふろのバーにまず干すため見えるしでこの時間はいつもここに連れてきます( ˘͈ ᵕ ˘͈ ).。.:*✧
送り出す前に最低でもここまでは済ませたいので朝はフル活動してます(* > <)⁾⁾
カップボード上なんかふきむらありますね:( ;´꒳`;):
あとでふきふきします笑
おはようございます♡
暮らしのひとこま♡
朝の風景✧
幼稚園に送り出す前の我が家のキッチン✧
冬でも麦茶しか飲まないので、水筒に麦茶いれて、おはしセットをカウンターの上に✧
置いとくと自分達で水筒カバーにいれたり、お給食袋におはしセットいれたりしてくれてます(*ᵕᴗᵕ)
朝一気に麦茶がなくなるので、朝食後に朝は麦茶づくりしつつ洗い物すませてます(´,,>ω<,,`)
べびちゃんはここだとキッチンにいるときはもちろん、白いドアの向こうはすぐ洗面所なので、ドアあければあたしが歯磨きや顔あらうのも見えるし、洗濯物もおふろのバーにまず干すため見えるしでこの時間はいつもここに連れてきます( ˘͈ ᵕ ˘͈ ).。.:*✧
送り出す前に最低でもここまでは済ませたいので朝はフル活動してます(* > <)⁾⁾
カップボード上なんかふきむらありますね:( ;´꒳`;):
あとでふきふきします笑