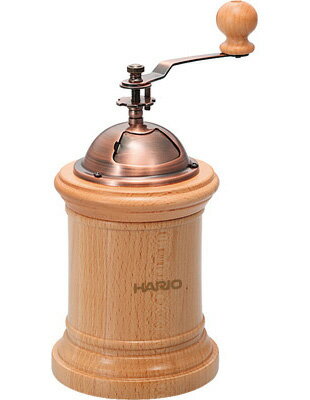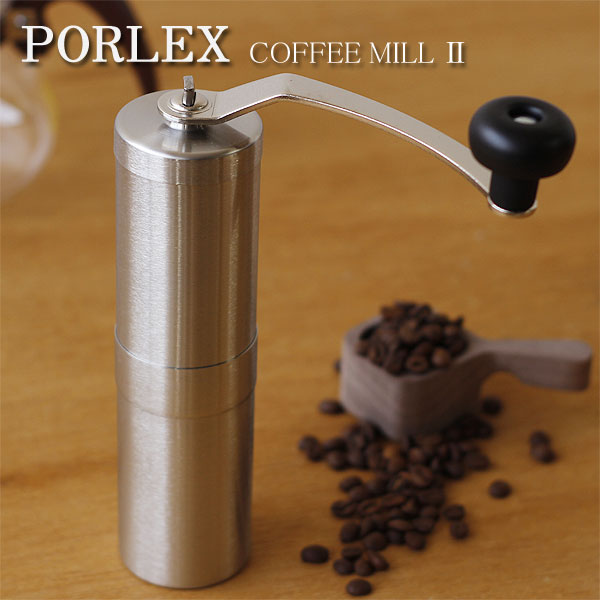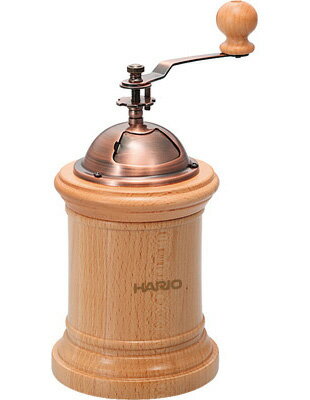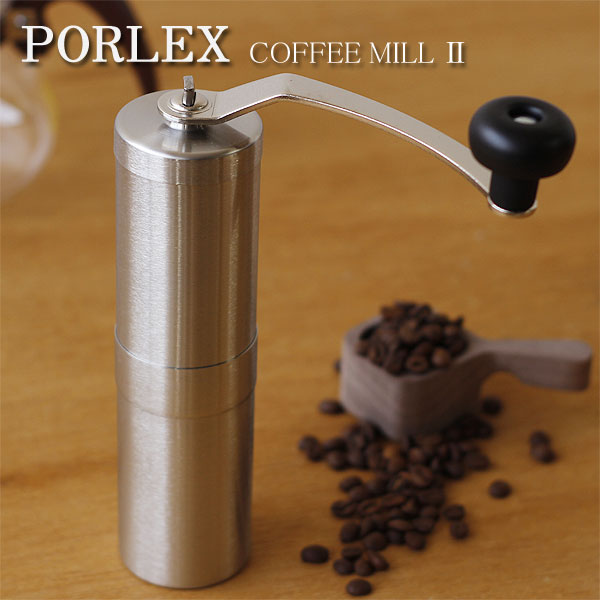先日アップしたサイドテーブルの製作過程です。
木工の組手で作るのは難度が高いので、手ノコでのカットとねじ止めでトライ。木材は強くて加工しやすいラワン材を使用。サイズは、天板が14×240×450、脚が14×45×約350~515、脚のつなぎ材が14×45×192。
① コの字型の構造を成立させるのがポイントで、縦の脚を少し斜めにし、下側の部材を浮かせて直角に木ネジで接合。上側の部材は脚に合わせた角度で先端をカットして木ネジで接合し、上端を金属プレートで補強。
② 天板裏の金属プレートが当たる箇所を、彫刻刀で削って高さを調整(彫刻刀使うのって何年ぶり???)。
③ 天板表のカップを置く場所も、彫刻刀でせっせと削りました💦。この後、各部材端部の丸み付けと面取りも、彫刻刀で実施。
④ オイル塗装後に、天板と脚をロの字の14㎜角材を介してねじ止めすることで一体化。その後、両脚をつなぎ材で3か所ねじ止めして完成。
手ノコは板の両面から少しずつカット、ねじ止めも板の両面から錐で下穴をあけることで、ずれ・曲がりを最小限に抑えました。それでも、組み立て時の歪みを修正するため、3か所のつなぎ材の寸法を変えてやり直し、脚の接地面で5㎜弱の高さ調整をすることで、何とかガタツキなく使える物になりました😅
…と、説明が長くなって恐縮です🙇💦
完成したサイドテーブルのPicはこちら↓
https://roomclip.jp/photo/ztH8
先日アップしたサイドテーブルの製作過程です。
木工の組手で作るのは難度が高いので、手ノコでのカットとねじ止めでトライ。木材は強くて加工しやすいラワン材を使用。サイズは、天板が14×240×450、脚が14×45×約350~515、脚のつなぎ材が14×45×192。
① コの字型の構造を成立させるのがポイントで、縦の脚を少し斜めにし、下側の部材を浮かせて直角に木ネジで接合。上側の部材は脚に合わせた角度で先端をカットして木ネジで接合し、上端を金属プレートで補強。
② 天板裏の金属プレートが当たる箇所を、彫刻刀で削って高さを調整(彫刻刀使うのって何年ぶり???)。
③ 天板表のカップを置く場所も、彫刻刀でせっせと削りました💦。この後、各部材端部の丸み付けと面取りも、彫刻刀で実施。
④ オイル塗装後に、天板と脚をロの字の14㎜角材を介してねじ止めすることで一体化。その後、両脚をつなぎ材で3か所ねじ止めして完成。
手ノコは板の両面から少しずつカット、ねじ止めも板の両面から錐で下穴をあけることで、ずれ・曲がりを最小限に抑えました。それでも、組み立て時の歪みを修正するため、3か所のつなぎ材の寸法を変えてやり直し、脚の接地面で5㎜弱の高さ調整をすることで、何とかガタツキなく使える物になりました😅
…と、説明が長くなって恐縮です🙇💦
完成したサイドテーブルのPicはこちら↓
https://roomclip.jp/photo/ztH8